帯にも大きくな見出し、「ここ数年で最高かつ最も独創的なお金の本」by ウォールストリートジャーナル
アマゾンレビューも10,000件以上、世界的ベストセラーのこの本。読書好き且つ、マネー本好きの僕が読まないわけにはいかない!と珍しくkindleではなく紙の本を購入しました。
大体、帯に踊らされて大したことが無い本が多い中、この本は帯通り、いや帯に書かれた事が大げさとは全く感じない程素晴らしい内容。
今回はこちらの本の概要紹介と、僕が特に印象に残った内容について書いていきたいと思います。
既に読み終わった方は共感頂ける部分有るかもしれないですし、まだ未読の方は是非手に取って読んで頂きたいと思います。
内容の概要

300ページを超えるボリュームありますが、字も大きく、語り口調で書かれており、スラスラ読めるので1日、2日で完読出来ます。
著者のモーガン・ハウセル氏は、ベンチャーキャピタル「コラボレーティブ・ファンド」でパートナーを務める現役の金融プロフェッショナル。そしてウォール・ストリート・ジャーナル紙などの大手媒体にファイナンス関連の記事を寄稿する気鋭のコラムニスト。
モーガン・ハウセル | 著者ページ | ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp)
全20章に分かれていて、最初から読まなくても気になる部分だけ読むだけでも理解可能な構成になっています。以下は目次のタイトル
- おかしな人は誰もいない
- 運とリスク
- 決して満足できない人たち
- 複利の魔法
- 裕福になること、裕福であり続けること
- テールイベントの絶大な力
- 自由
- 高級車に乗る人のパラドックス
- 本当の富は見えない
- 貯金の価値
- 合理的>数理的
- サプライズ!
- 誤りの余地
- あなたは変わる
- この世に無料のものはない
- 市場のゲーム
- 悲観主義の誘惑
- 何でも信じてしまうとき
- お金の真実
- 告白
各々とても面白い内容なので、是非全て読んで貰いたいですが、僕が特に印象に残ったのは以下になります。
はじめに リードおじさんの衝撃的な事実
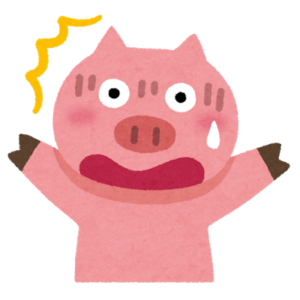
本書を開いて5ページ目から衝撃を受けます。
リードさんというガソリンスタンドで接客と自動車整備の仕事を25年勤め、百貨店で17年パートタイムで働いていた普通のおじさん。
2014年に92歳で亡くなった時、この田舎の地味な清掃員の死は国際的なニュースに!
何故なら死亡時に800万ドル以上(現在の日本円で8億円以上)もの純資産を持っていたからです。知人たちは驚きました。宝くじ当たったわけでも、遺産があったわけでもないのに。
なぜリードさんがこれ程までの資産を持っていたのか。理由は2つ。それは節約と、優良株への投資を行っていたから。節約で貯めた小さな投資は時間と共に大きくなり莫大な資産を築き上げたのです。
以前、ブログで小金持ちになる力をご紹介しました。リードさんは稼ぐ力こそ強くなかったものの、貯める力、資産運用力が人よりも大きく秀でていた方。そして時間の助けも借りて、ここまで大きな資産を築いたという事で、凄く勇気を貰える話です。

なお、リードさんは200万ドルを義理のお子さんへ、600万ドルを地元の図書館と病院へ寄付されています。素晴らしい!
こんな感じで最初からグイグイ引き込まれていきました(笑)
3章 決して満足できない人たち

この章におけるキーワードは「足るを知る」という言葉。
著者は、現代社会には「これで十分だ」という感覚が欠如している。それは莫大な富や権力を手にした者にも当てはまると言います。
事例として、超有名企業のCEOで大金持ちになったが欲を出して違法行為で捕まった事例、同じく既にお金持ちだったはずの富豪が詐欺を働き地位も名誉もどん底まで落ちた男の話が挙げられています。
この「足るを知る」を身に着けるために心得るべき事が4つあります。
- 動き続けるゴールポストを止める
- 富の比較ゲームに参加してはいけない
- 吐くまで食うな
- 大きな利益が得られる可能性があっても危険を冒す価値の無いものは多い
特に1番目の「動き続けるゴールポストを止める」はスキルとして、とても重要と著者は強調しています。なぜなら努力をして結果を手にしても、それに合わせて求める基準を上げ続けるのなら「もっと多く」の金、権力、名声を手に入れたいという欲望にかられ、満足感よりも野心の方が大きくなるから。
これは非常に危険な状態です。1歩前進する毎に、ゴールポストが2歩前に動く。求めるものがどんどん遠くに離れていく。結局追いつくには大きなリスクを取る必要が出てくるのです。
「十分」の感覚がなければ幸せは遠のきます。野心が強く大きな目標を持つ事は大事ではありますが、野心がエスカレートすると、前述の2人のように悪の道に踏み外す事もありうるのです。
7章 自由

著者は、最高の豊かさとは、毎朝、目を覚ました時に「今日も思い通りに、好きなように過ごそう」と思える事だ、と言い切ります。
人は「幸せになりたい」から経済的に豊かになろうとする。何をもって幸せとするかは人それぞれで定義は難しい。しかしながら誰にとっても共通の要素はある。それは
「思い通りの人生を送れること」。
好きな時に、好きなだけ、好きなことが出来る。
それは何物にも代えがたい価値。
これこそがお金から得られる最高の配当だと。
心理学的にも、人間に幸福感をもたらす信頼性が高い要因は「人生を自分でコントロールしている」というはっきりとした感覚がある事のようです。
僕も含め日本人の多くがサラリーマン。つまり自分でコントロールする事は物凄く少なく、会社の、上司の、先輩の、取引先から指示、目標を与えられ、それの対価として給与をもらっています。
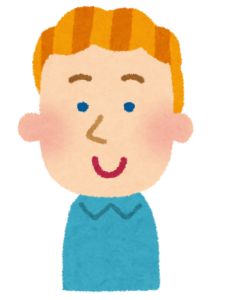
著者は大学生の時、憧れていた投資銀行で夏季インターンシップをする機会を得て、宝くじに当たったも同然と思っていました。投資銀行に憧れていた理由は単純明快。どの業界より給与が高かったから。
しかし初日でなぜ投資銀行の仕事は高収入かが直ぐに分かったそうです。彼らは人間の限界を超えるようなレベルで長時間働いているから。大抵の人にはまず耐えられないほどの激務。深夜0時前に家に帰れるのは贅沢だと考えられるほど。
現代の米国は、世界史上最も豊かな国。でも富や所得がはるかに少なかった1950年代に比べ、現在の米国人が幸福だと示す証拠は殆どありません。豊かになった米国人は大きくて質の良いものを買えるようになった。だが同時に自分の時間をコントロールできなくなった。
米国だけでなく日本も同様。インフラも整い、医療も何不自由なく、多くの国民が餓死する心配がない。でも以前と比べ物質的には豊かにはなったが、心は貧しくなった人が少なくないと感じます。

カール・ピレマーの著書「1000人のお年寄りに教わった30の知恵」の中で、米国の高齢者1000人にインタビューを行い、彼らが長い人生経験から学んだ最も重要な教訓を探ると、彼らが大切にしていたのは以下3つ。
- 豊かな友情
- 高貴で大きな目的の為の活動への参加
- 子供達とゆっくり過ごす充実した時間
どれもが必ずしもお金を沢山必要とはしないものばかり。つまり、結局人は最後は家族や友人に囲まれて、安心しながら最後を迎えたいのですね。
また、彼らはこんな事も言っていたようです。
「子供たちは、親のお金(またはお金で買えるもの)を欲しがったりしない。子供達はただ、親が一緒にいてくれることを望んでいるのだ」
僕はこの言葉にドキッとさせられました。子供達との貴重な時間を犠牲にして仕事優先し過ぎていないか、疲れたからと言って子供達との遊ぶ時間を放棄していないか。子供達との大切な時間を後悔無いように過ごさないといけないと改めて思いました。
ロレックスが教えてくれた本当に大切なモノ – みるきぃ 身近な投資のおはなし (milky-happylife.com)
10章 貯蓄の価値

冒頭、著者は読者に説得を試みます。それはお金を貯める事の価値について。
ある程度の収入がある人は、3つのグループに大別できる。
- 貯金をする人
- 貯金は出来ないと考える人
- 貯金する必要など無いと考える人
②、③のグループの為に、貯金すべき理由を分かりやすく説明してくれます(笑)
ここで非常に重要な言葉を述べています。それは「富を築くには収入や投資リターンは殆ど関係なく、貯蓄率が大きく影響する」という事。
投資リターンが多ければお金は増える。でも不確実。
一方、エネルギーの世界の省エネや効率化と同様、個人がお金を貯蓄し、倹約する事は「お金を増やす方程式」において、私たちが唯一コントロールできる部分であり、将来的にも確実な効果が期待できる。
まさしく貯める力は強し!僕自身の最大の強みです(笑)
この章で心に突き刺さった言葉をあと2つ共有します。
収入 - エゴ = 貯蓄
著書は貯蓄の式を凄くシンプルに、分かりやすく書いてくれています。
一定の生活レベルが満たされた時、それ以上に何かが欲しくなるのは見栄や他人との比較が原因。富を築く人は、他人の目を過度に気にしないという傾向があるとの事。
目的のない貯金が最大の価値を生む
著者は特定の目的が無くても貯金はすべきだと主張します。それは人生では最悪のタイミングで予期せぬ出来事が起こりえるから。貯蓄はそのリスクに対する備え。
- 目的の無い貯蓄をすれば、選択肢と柔軟性が手に入る。
- 貯金があれば待つべき時はじっと待てる。
- チャンスが来たら飛びつくことも出来る。
- 考える時間も作れる。
- 自分の意志で人生を軌道修正できるようになる。
これは本当にその通りだと思います。長い人生何があるか分かりません。中には資産を全てリスク資産へ投資されている猛者もいますが、僕自身は現金はかなり多めで、運用資産はまだ全体の内の2割程度。
これからリスク資産への割合は増やしていくつもりですが、少しずつ自分の許容できる範囲内で進めていこうと考えています。
13章 誤りの余地

これも当たり前のようだが、見落としがちな点。
「誤りの余地」について、著者はリスクをあまり取ろうとしない人や、自分の考えに自身がない人の為の消極的な方法だと思われがちだが、逆で攻めの戦略という。
誤りの余地を残しておくほど、どんなことにも耐えやすくなる。この耐久力があるからこそ、時間を味方につけ、長期間にわたって勝負を続け、低確率の結果からしか得られない最大の利益を手に入れやすくなるという。
最大の利益を手にする機会はめったに起こらない。そもそも発生頻度が少なく、複利の効果が生じるには時間を要する。
投資で「誤りの余地」をつくるべき2つの場面があるという。それは
- ボラティリティ=価格変動リスク
- 老後資金の為の投資
ボラティリティ、つまり大きな価格変動。あなたは資産が3割減っても平気か?と著者は質問する。普通の人は精神的に耐え切れず損切を選ぶ人が大半。大きな損失を出した後、疲れ切って投資を止めてしまった人を沢山見てきてるという。エクセルの計算上は耐えられても精神的には耐えられないことがある。
老後資金について。もし自分の退職日が2009年のような極端な下げ相場の真っ只中にいた場合、どれ位の人が怖気づかず耐えきれるだろうか。また若い時に突然、高額の医療費が必要になったら?
これらの「もしも」に対する答えは「若い頃に想定していた老後生活は送れなくなる」。最悪の事態すら起こり得る。解決策は簡単。将来の利回りを見積もる時に「誤りの余地」を残しておくこと。幸福感を得るための最良の方法は、目標を低く設定すること。
著者の理屈は保守的過ぎる、と考える人もいると思う。しかし日本の東日本大震災での原発事故や、第二次世界大戦のドイツ軍の戦車がまさかの野ネズミにより電気系統を破壊され動かなくなった事など。予想出来ない出来事がいつ起こるか分からない。
備えあれば患いなし。日本の諺からも学ぶ事は多い。

総評

本書は最近読んだ本の中でも1,2を争うくらい素晴らしい本でした。
今回は自分の備忘録も含め、ブログに特に心に残ったフレーズや考え方を纏めてみました。上記以外にも沢山の示唆に富んだ、多くの事例や失敗談などが豊富に掲載されています。
是非手に取って読んで頂き、ご自身の知識の一部に、そしてこれからの投資スタイルの参考して貰えたらと思います。






